こんにちは、花森すみれです。
わたしには、叶えたい夢があります。
それは、「日本の教養を、世界に広める」というものです。
なぜなら、日本だけが世界を変える力を持っており、もしすべての日本人がその自覚を持って、自己を磨き、そしてその力を世界に発揮することがあれば、世界が根底からガラリと変わる。
そう本気で信じているからです。
何百年と支配してきた「西洋文明」と、日本文明の劇的な交代劇。
「小さな孤立文明である日本が、いま行き詰まりを見せている西欧文明に代わって、人類社会がこれから目指すべき新しい目標を示すことができる」ーー。
そういう主張をされたのが、『日本の感性が世界を変える』という著者を書かれた、鈴木孝夫さんです。
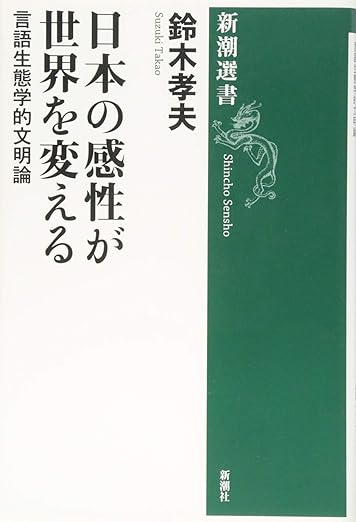
この本には、こう書かれています。
この小さな孤立した異質の日本文明が、これまで世界を大航海時代以後数百年にわたって支配してきた西洋文明と、嫌でも交代せざるを得ない劇的局面を、いま人類が迎えているというのが、この本の中で私の展開する文明論の骨子に他なりません。
(日本の感性が世界を変える」p12)
今までの世界は、「西欧的価値観」が主流だった。
この何百年の間、わたしたちは「西欧文明」が定めた価値観によって、人生のレールや、人間の幸福の価値というものを定められてきました。
それは資本主義に支えられた、「とにかく多くの物を所有している人間が幸福である」という価値観に沿った人生のレールや幸福感です。
いい大学を出て、いい会社に行き、とにかく多くのお金を稼ぎ、生きているうちにより多くの物を所有する。
誰もが羨む結婚相手、子供、家、車、装飾品……そうしたモノを生きているうちにどれだけ多く手にいられるかで、ひとの幸福というものの尺度が決められていました。
「西欧的価値観」の行き詰まり
しかし現代、ここにきて、そうした何百年と続いた「西欧文明的価値観」が行き詰まってきました。
十六世紀始まる大航海時代以後現在まで、世界はあらゆる意味で西欧文明の主導する時代でした。ところがその時代が今まさに終わりを告げようとしています。それはこの人間中心主義(または人間至上主義)に裏打ちされた、理性と論理を極端に重視する西欧文明が、いろいろな点で行き詰まりを見せ始めているからです。
(同上 p9)
「物質的な豊かさによる幸福」への疑問。
「好きなことで生きていく」ーーそうした言葉を、ここ数年、よく耳にするようになってきました。
それはつまり、今までの「いい大学を出て、いい会社に出て、とにかくお金を稼いで、多くの物を所有すれば幸せ」といった決まりきった画一的な「幸福」や「価値観」に、疑問を投げかけるひとが現代になって圧倒的に増えたということだと思います。
自分の好きなものは自分で決める。何を所有し、どれだけ所有するかは自分で決める。自分の幸福は自分で決める。
物理的な豊かさよりも、精神的な豊かさを求める考えに移行していっているということであり、それはとても良いことだと思います。
限られた席をめぐっての熾烈な競争社会。
勿論、「いい大学に入って、いい会社に入って、物をたくさん所有する」という幸せが悪いというわけではありません。
問題なのは、そうした幸福を得られるひとは、かなりの少数派であるということです。
そのためその限られた席を巡り、熾烈な競争社会となりました。
いい大学に入るための受験にそなえるため、幼い頃から皆同じような場所に閉じ込められ、同じような知識を知識をとにかく詰め込まれる。
それが終わったら、次はいい会社に入るための競争、会社に入ったあとはいい地位につくための競争、その地位を維持し続けるための競争……。
私生活でも、「どれだけ自分が幸せな人生を送っているのか」ということを示すために、SNSに自分が所有しているもの、豊かな生活を、競い合うように誇示する。
そしてそれを得られないひとたちの足の引っ張り合い、妬み、やっかみで、SNSはしばしば戦場と化しています。
競争自体が悪いというわけではありません。
しかしその競争をしているひとたちのなかに、「そもそもこれほど苦しんで目指している、その席は自分にとって欲しいものなのか? 本当にこれが自分にとって幸せなのか? 自分の個性を活かした生き方が他にあるのではないか?」と冷静に考えているひとがどれだけいるでしょうか?
そんなことを考える時間や余裕を幼い頃から与えられず、とにかく争え、その限られた席を取り合え、というプレッシャーに日々晒される。そしてそれが一生続く。
その争いに疲弊し、引き篭もってしまったり、自ら命を絶ってしまうひともいるのです。
限れられた資源をめぐっての環境破壊。
さらに「物質的な豊かさ」だけを目指す幸福や価値観は、いまでもこの地球の環境を破壊し続けています。
私の見るところ、これまでの西欧型の近現代人の目指す目標は、人間の幸福と繁栄のみであり、それに向かって止め処のない生活向上や技術の発展を求め続けたために、自然界の安定した秩序を殆ど回復不可能にまで破壊してしまいました。
(同上 p9)
当たり前ですが、この地球上の資源は限られています。
それにも関わらず、「より多くのものを所有する方が幸せ」という価値観を続け、それにともなう競争社会を何百年と続けた結果、どんどん資源が減っていき、持続が難しい社会になっていっているのです。
物質的な豊かさを求める「西欧的価値観」から、精神的な豊かさを求める「日本的価値観」への大転換をめざす。
では、その「西欧文明の価値観」に変わる、「日本文明の価値観」とは、いったいどういうものなのでしょうか?
「生きとし生けるものはみな繋がっている」という自然観。
なぜ小さな孤立文明である日本が、いま行き詰まりを見せている西欧文明に代わって、人類社会がこれから目指すべき新しい目標を示せるのかというと、(中略)未だに「生きとし生けるものすべては、互いに複雑な共存共栄の無数の網目でつながっている」という、今ではほとんどの大文明が失ってしまった、古代のアニミズム的で汎神論的な自然観を、未だにかろうじて保持している唯一の、しかも強力な先進近代国家だからです。
(同上 p12)
日本人であるわたしたちにとって、「生きとし生けるものはみな繋がりあっている」「人間と自然は対等につながり互いに循環している」という価値観は、ごく当たり前のように根付いているものです。
普段は意識していなくても、わたしたち日本人の行動や、生き方に、自然にその価値観があらわれています。
それは西欧諸国にはない価値観であり、先進国のなかで日本だけがかろうじてそれを保持しているというのです。
だからこそ、人間はこの地球上のすべての命あるものとの共存共助の輪でつながっているのだ、人間だけにこの世で他を押しのけて生きる権利があるのではないという、日本人がまだ完全には失わずにどこかに持っている柔らかい謙虚な気持ちを、広く世界の人に知らせ広めること、それも一刻も早く行なうことが、目前に迫っている人類の危機をいくらかでも回避するために絶対に必要なのです。
(同上 p27)
白黒はっきりさせないで曖昧なままに飲み込む能力
アメリカなどでは好きか嫌いか、善か悪かという発想が強い。(中略)ハリウッド映画を見ていれも善悪がはっきりしていますが、日本の文楽や能を見ていると違います。みんなが義理と人情の狭間で、正解がない問題に苦労しています。現実には白黒、善悪で割り切れないことがあるという感覚が日本の文化、芸術に表れていると思います。(中略)
善人といえども百パーセント善ではなく、また百パーセントの極悪人もいないというのが日本的な考え方だと言われるのです。
(同上 p43)
日本人はよく自己主張をしない、自分のために闘わない人種だと批判されます。
しかしできるかぎり善悪をはっきりさせず、「争いを避ける」というのは、決して悪いことではないですし、
むしろこれからどんどん進んでいく多様性の時代において、日本特有の「曖昧なままで受け入れる力」というのは、平和な社会の基盤となるものではないでしょうか。
持続可能な、平和な社会。
「日本は平和な国である」というのは、世界から見ても有名ですし、わたしたちも自覚していることだと思います。
それには上に挙げたように日本文化特有の性質が「他者との対立を避け、共存を大切にする感性的な生き方」(「日本の感性が世界を変える」p52)を自然とわたしたちにさせているからです。
勿論他にも理由はあるでしょうが、この日本文明における生き方は、これからの世界にアピールするべき価値のあるものですし、
これまでの日本人の先輩たちが培ってきた「持続可能な平和な社会」を、わたしたちが受け継ぎ、受け継ぐだけではなく世界中に広めていくこと。
それが日本人であるわたしたちに課された重大な義務であると思います。
世界に広めたい、「日本の教養」とはなにか。
では、わたしが世界に広めたいと思っている「日本の教養」とは何か、ということを具体的にお話しします。
- 「日本語」
- 「日本文化」
- 「両性平等」
日本語
まず、わたしが世界に伝えたいと思っているのは「日本語」です。
なぜならわたしたちの使ってる「日本語」には、わたしたちの文化、精神が宿っているからです。
言語が変わると、性格が変わると言われます。外国の方で、日本語を使うようになって「性格が優しくなった」「礼儀正しくなった」「穏やかになった」という話も耳にします。
よく日本語は美しいといわれますが、言語が美しいから、わたしたちの心も自然と「美しいもの」を求めてしまうのかもしれません。
「日本語」は、世界に伝えるべき素晴らしい財産です。
日本文化
日本文化も、当然、世界に伝えるべき重要な財産です。
日本の「食文化」「観光」の素晴らしさは、もはやいうまでもありませんが、「瞑想」などの精神との向き合い方、何かひとつのことを突き詰めて極めきる「日本の心」も同時に伝えていきたいです。
両性平等
残念ながら、まだまだ世界は両性平等とはほど遠い社会です。
特に日本はジェンダーギャップで先進国で最下位を維持するなど、世界的に見ても男女不平等の国で有名です。
しかしわたしは、もし世界で初めて真の両性平等の世界が実現するとしたら、それは日本であるべきだと思っています。
というと、反論される方がほとんどだと思います。そんなわけがない、と。
しかし、かつての日本は「両性平等」の国でありました。
私たち日本人は、じつは「男尊女卑という心の遺伝子」は、持っていないのである。(中略)
いや。そんなことはないはずだ。日本史の中にあっても、やはり女は虐げられたきたではないか。歴史の中心は、常に男だったではないか。「男尊女卑」の心は、日本人にも厳然として宿っていたではないか。
ーーと、あるいは反論する人も多かろう。
そのとおりである。日本にも「男尊女卑」はあった。ところが、じつはそれは「日本人の本来の心」から自然派性したものではなかったのだ。(中略)
彼らは、手っ取り早く「中国の文化を真似する」というお手軽なやり方で、文化を育んだ。
それが、日本古代の飛鳥時代から奈良時代、そして平安時代である。(中略)
ところが前にも述べたとおり、日本以外の文化圏は、根本的に「男尊女卑」なのである。したがって当時の日本人たちは、「この男尊女卑という人間観」までをも輸入してしまった。
かくして日本にも、中国の真似事から始まった「男尊女卑の文化」が定着した。
(「広岡浅子 気高き生涯」p22)
それが中国から儒教の考えを取り入れてしまったことによって、「男尊女卑」の文化になってしまったのです。
だがそれはあくまで外部から取り入れられたものであり、日本の本質的な文化ではありません。
さらに日本は国民の大部分が無宗教であるという、特殊な国です。どの宗教にも基本的に男尊女卑の思想が強い中、その宗教に頼らずに自身を立てることができる。
そんな特殊な日本人こそ、率先して両性平等を実現する。そうすることによって、日本は「世界の模範」として、ますます世界中から尊敬される国になることができると、わたしはそう信じています。
世界を変えるには、まず日本が変わる必要がある。
人類の目指すべき目標が発展から縮小へと大転換を迫られているとき、これまでのような外へ外への限りない膨張拡大ではなく、(中略)人間の持つ発展向上のヴェクトルを逆転させて、内に向ける生き方を人類が否応なく迫られている今こそ、超大国の一つとなった日本は、これまでのもっぱら外に学ぶ日本から、積極的に外に教える日本へと、国家の性格を反転させる精神革命を起こすべきなのです。
(「日本の感性が世界を変える」 p106)
世界を救うには、まず日本人が変わらなければならない。
そして自分たちの使命を自覚し、世界に出ていく必要があると思います。
今こそ、「日本人の誇り」を取り戻すべき。
世界で最も恵まれた現在の日本人が、ただその豊かさと安全を無自覚に享受しているだけでは、ひとり我良しの経済大国に過ぎないのであって、日本の根本にある日本型文明の感性を世界に伝え教え、人類の方向性として積極的に指し示すことが二十一世紀に求められているのです。その意味で今日本人に課せられているのは、人類の文明史的使命であるといっても過言ではないのです。
(同上 p240)
まず日本人がするべきなのは、「日本人としての誇り」を取り戻すことです。
どうしてもわたしたちはヨーロッパの国の方が優れていると思い、自分たちの国を下に見てしまいます。
しかし、日本の文化、歴史、生き方、考え方。
そしてそれが世界にどのように評価されているか。
それをきちんと知ることで、「日本人でいることの誇り」を取り戻すことができ、
自然と「自分たちが世界に何をすべきか」という使命感に目覚めることになっていくと思います。
そうしたひとたちが少しずつ増えていくことで、やがて世界を変えるほどの力になっていく。
わたしはその手伝いができるような発信をしていきたいです。